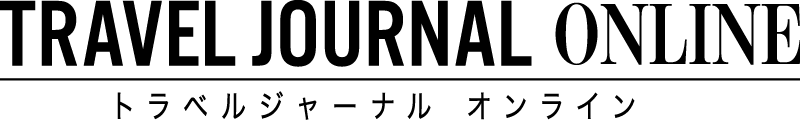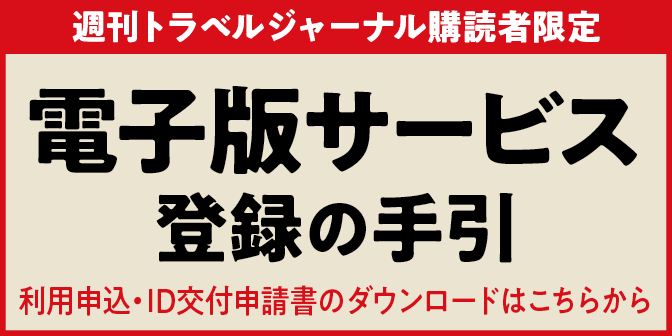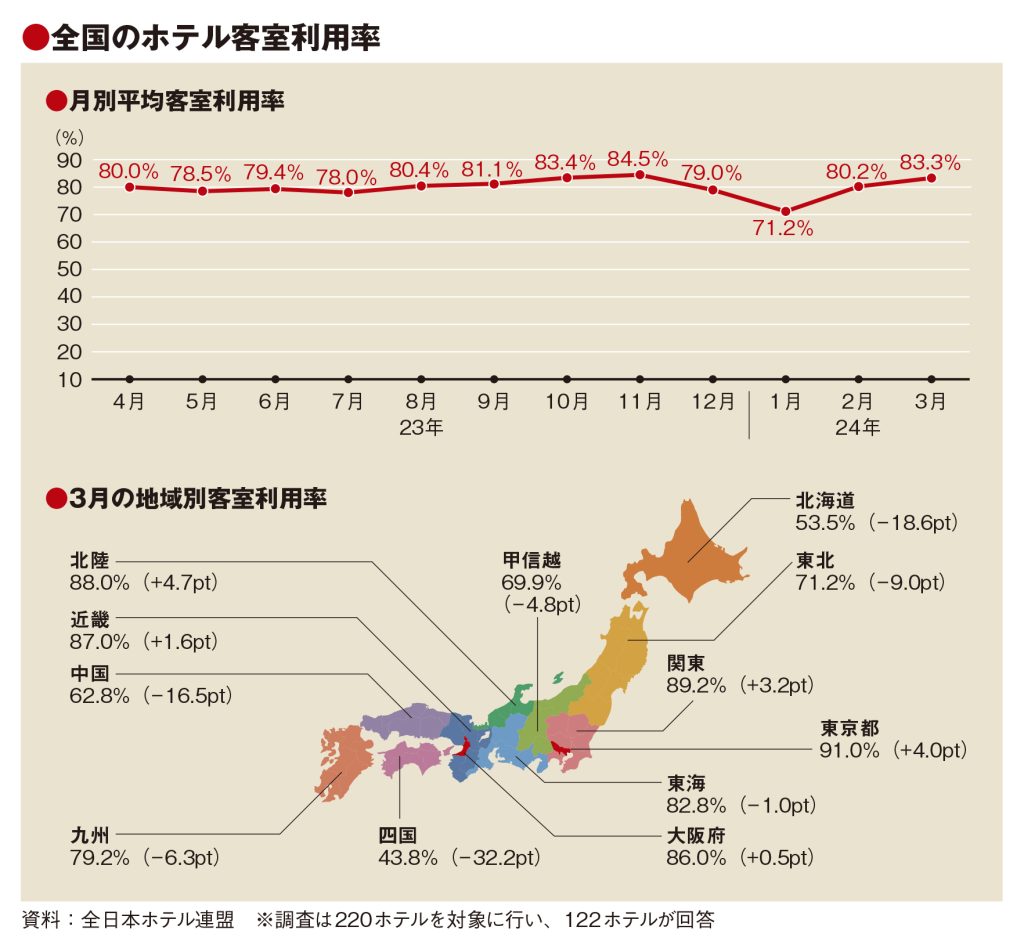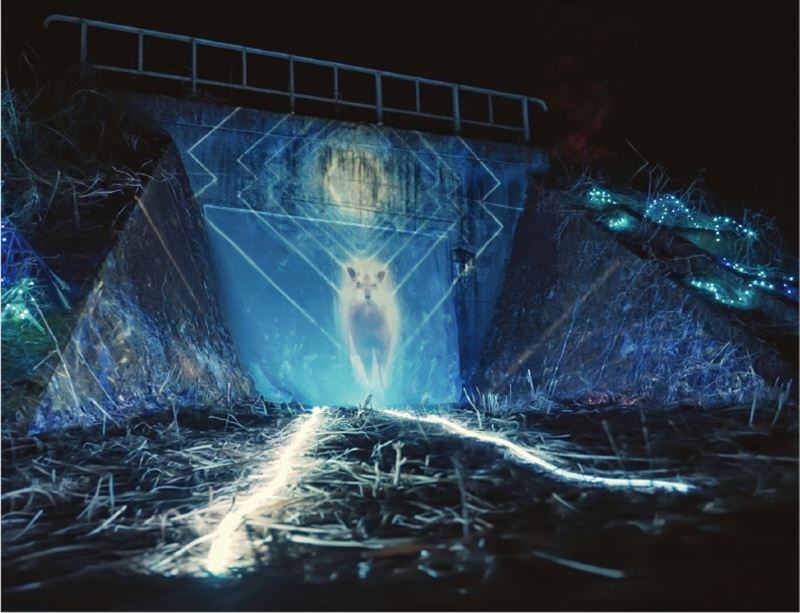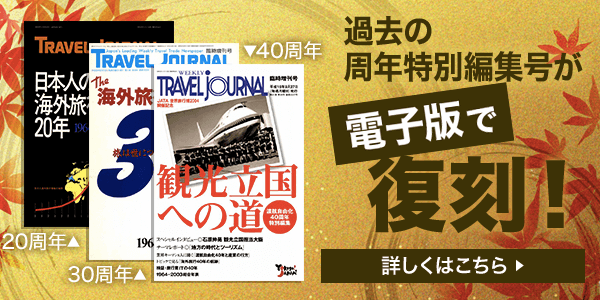旅費規定のジレンマ 料金高騰とのはざまで
2023.09.11 00:00

物価上昇などに伴う海外旅行費用の高騰が需要回復に影響を及ぼしている。それは、レジャー目的に先行して回復が進む業務渡航にとっても懸案事項。旅費の上限規定と実勢価格の乖離が大きいためだ。旅費規定のジレンマは早期回復が望まれる修学旅行にも影を落としている。
世界的な物価上昇や急速な旅行需要の回復などを背景に、旅行費用が高騰している。日本ではこれに輪をかけて円安が費用上昇を加速させている。海外へのレジャー旅行の回復を阻む大きな足かせだ。一方で自らの懐が痛まない業務渡航は影響が相対的に少ないと考えられるものの、実勢価格が旅費規定の上限を大きく上回る状況が生まれている。それが常態化すれば、需要そのものにも影響が出かねない。
コロナ禍前後の海外旅行の回復率を見ると、業務渡航が全体をけん引しているのが分かる。観光庁発表の主要旅行業者43社の取り扱い状況を基に、JATA(日本旅行業協会)が1~4月の海外旅行取扱高を各社の事業領域に基づきカテゴリー分けしたところ、19年同期に比べ業務渡航の回復率は65.8%に達し、全体の35.1%を大きく上回る。これに対し、レジャーは22.3%にとどまった。業務渡航が勢いを失えば海外旅行の立ち直りがさらに遠のいてしまう可能性すらある。そんな懸念を大きくしかねないのが、旅費の上限規定と実勢費用の乖離なのだ。
出張の際の旅費規定は民間企業の多くが社内ルールとして設定している。経費の無駄遣いを防ぐと同時に、出張費用を確実に経費として処理できるようにすることで法人税の節税対策にもなるからだ。旅費規定の金額をどうするかの制約はなく、各企業が自由に設定できるが、相場を大きく外れた高額な旅費を設定してしまうと会社の支出が増えるだけでなく、監査や決算時に経費として否認されることも考えられる。
一方、国や地方自治体などに所属する公務員の出張も、税金の無駄遣いにつながらないように法律や条例に基づく旅費規定が設けられている。例えば国家公務員の場合は、国家公務員等の旅費に関する法律(旅費法)に準拠した旅費支給規定によって上限が定められている。
民間企業の旅費規定は、株式会社の場合、変更するには株主総会の決議が必要だし、公務員の場合は法律や条例の改正が必要となる。いずれにしても変更は簡単ではない。従って、旅費規定は交通費や宿泊費の状況を把握したうえで慎重に決める必要があるが、現在のように交通費や宿泊費が急騰すると対応が後手に回ってしまうリスクが生じるわけだ。
1年でホテル代1~5割増し
民間企業も国・地方自治体も、旅費規定の組み立て方はほぼ同じだ。基本的に規定内容は国内出張と海外出張に分けて交通費や宿泊費が設定されている。海外出張の場合、出張者の役職や職階によって利用できる航空座席のクラスや滞在地での宿泊費の基準が設けられる。加えて宿泊費に関しては現地の物価事情を加味し、滞在地域別の基準や上限を設けるのが一般的だ。
例えば民間企業A社の事例を見ると、北米・欧州と東南アジアでの宿泊費は取締役がそれぞれ3万円/2万5000円、部長職が2万5000円/2万円、課長職が2万円/1万8000円、係長職が1万8000円/1万5000円、主任・社員が1万4000円/1万円といった具合だ。
国家公務員の場合は対象地域が北米・西欧・中近東、東欧・オセアニア・東南アジア、中国・南アジア・中南米・アフリカのほか、指定都市として北米のニューヨーク等4都市、欧州のロンドン等4都市、中東のクウェート等4都市、アジアのシンガポール、アフリカのアビジャンで合計14都市が指定されている。そのうえで内閣総理大臣・最高裁判所長官、国務大臣、その他の者、指定職の者、7級以上(本府庁の課長、室長など)、6級以下3級以上(本府庁の課長補佐や係長など)、2級以下(本府庁の係員など)に分けられている。
カテゴリ#カバーストーリー#新着記事
アクセスランキング
Ranking