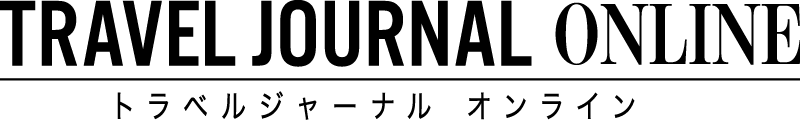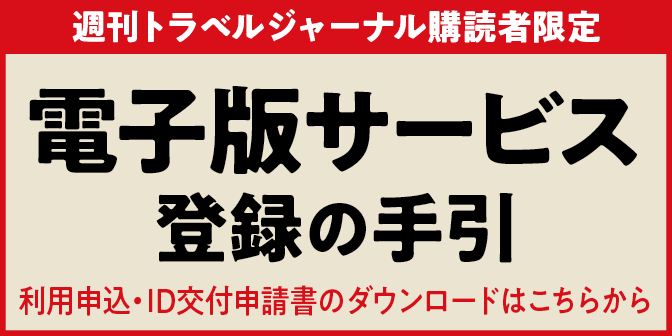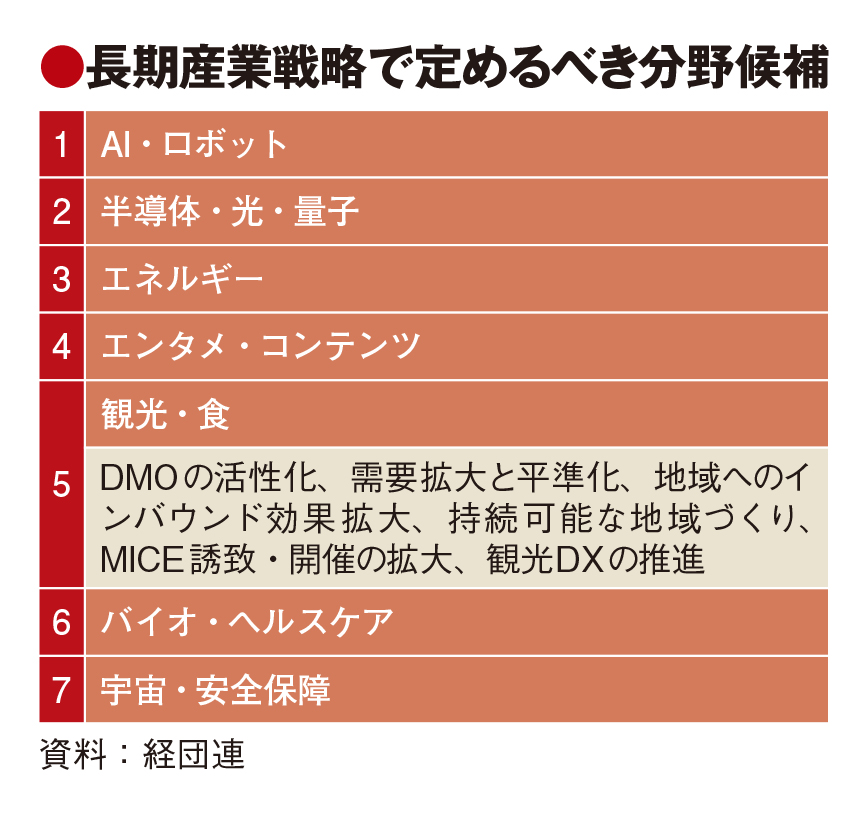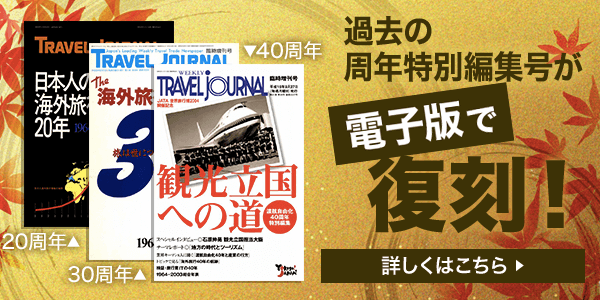LGBT法の運用
2023.07.10 08:00

いわゆるLGBT法と呼ばれる「性的指向及びジェンダーアイデンティティの多様性に関する国民の理解の増進に関する法律」が成立した。特に大浴場を持つ宿泊施設からは不安の声が多く聞こえる。私なりに現状を整理したい。
まず前提として、この法律は個人の行動を制限したり、新しい権利を与えたりするものではない理念法であることを理解しなければならない。法案の説明資料にも「現憲法や法体系の下で、マジョリティの女性の権利や、女性用スペースの侵害は許されない」「女湯や女性トイレを覗くといった目的で自分は女性だと主張し、施設管理者の制止を振り切って勝手に侵入すれば建造物侵入罪や、公然わいせつ罪などの犯罪に当たる」「公衆浴場法第3条で営業者の風紀維持が義務付けられており、これを受けた条例において、概ね7歳以上の男女を混浴させないと定められている」「ここでの男女とは身体的な特徴の性をもって判断することとされているため、公衆浴場の事業者は“体は男性、心は女性”という方が女湯に入らないようにする必要がある」「この取扱いは風紀の観点から合理的な区別であり、法の下の平等を定めた憲法 14 条に照らしても差別に当たらないとの政府答弁が示されている」などの文面が見られ、立法側としては大きな不安は感じていないようだ。
われわれも過度に警戒する必要はないのだろうが、悪意を持った客とのトラブルの解決が事業者の責任になっていることに対する不安は拭えないため、立法府の解釈が得られたいまのうちに、トラブル防止のため業界としての統一指針の策定や宣言を発表しておく必要があるだろう。
しかし、司法の場で上記説明における解釈が常に通じるという確証はない。すでにトイレに関してはLGBT寄りの判例が増えている。米国では学校において性自認に基づいて男子トイレを使うことを許されなかった生徒の訴えが米連邦最高裁判所においても支持されることとなった。日本でも経済産業省職員が戸籍上の性別を変更していないことを理由に職場で女性用トイレの使用を制限されたことで国を訴えた裁判で、一審は違法、二審は適法と判断され、最高裁に持ち込まれている。これらのポイントは「だれでもトイレ」の利用を勧めることも違法だと判断され始めたということだ。自認する性のトイレを使用したいという要望を断れば事業者の責任になる可能性は排除できない。
また、上記説明資料では公衆浴場法が根拠として例示されているが、外来客を受け入れていない宿泊施設は公衆浴場法の対象外であることも多い。逆説的に言えばそれらの施設ではトランスジェンダーの入浴を断る根拠がないということになりかねない。そもそも憲法24条には婚姻は「両性の合意」のみに基づくと書かれているが、最新の判決では法律婚から同性婚を排除しているのは憲法違反という解釈が示された。
男女・雌雄のことだと辞書にも明記される「両性」の解釈が司法の場で変化するのであれば、浴場の区分が否定される日が来るかもしれない。条令等で規定される「男女」の定義が身体上の性であることを、解釈ではなく明記するべく働きかける必要もあり得る。
別の角度から、例えば宿泊予約時に「俺は女湯に入る」と宣言され、その客の宿泊を断った場合、旅館業法上の宿泊拒否問題に関連付けられる可能性があるのではないかという指摘もあった。差別を否定しつつ、大多数の利用者の安心と安全を確保し、事業者のリスクを減らすために何の要素が足りないのか。いまは努めて冷静に、今後起こり得る可能性を分析する段階だ。

永山久徳●下電ホテルグループ代表。岡山県倉敷市出身。筑波大学大学院修了。SNSを介した業界情報の発信に注力する。日本旅館協会副会長、岡山県旅館ホテル生活衛生同業組合理事長を務める。元全国旅館ホテル生活衛生同業組合連合会青年部長。
カテゴリ#コラム#新着記事
-
?>
-

EUの新たな民泊規制法
?>
-

旅と文化資本
?>
-

次世代がつくる観光の未来
?>
-

キャパシティー
?>
-

生かすも殺すも
?>
-

ギリシャのオーバーツーリズム
?>
-

ラグジュアリートラベルへの道
?>
-

ライドシェアの方法論
アクセスランキング
Ranking