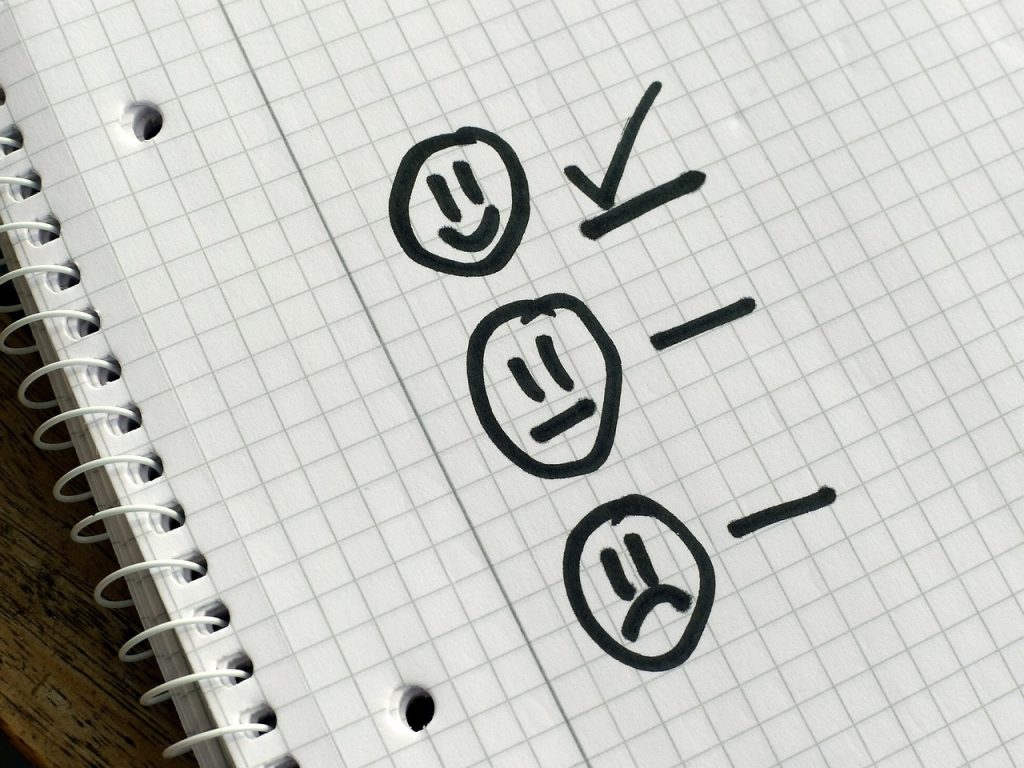旅行屋の矜持
2025.03.30 08:00

旅行会社に内定をもらったという学生から相談を受けた。旅行業に魅力を感じている。しかし、オーバーツーリズム、文化の見世物化、気候変動など観光の悪影響を自分が助長してしまうのではないかと危惧している。この矛盾をどう整理したらよいのかという悩みだった。
「旅が好きだから」「仕事で旅行ができそうだから」を理由に旅行業を目指した時代とは全く違う。憧れだけではなく、現実的な選択をしようとするのがいまの若者の悩みである。ある意味しっかりしている。
「君が持つ問題意識は悪くない。いまの時代に憧れだけで入社するのは観光の素人だ。君は傍観者ではない。観光の功罪を知ったうえでより良い旅とは何かを問いながら実践しなさい。君自身が旅行文化をつくる当事者になるのだから」と諭す。
正しい答えなのかは分からない。しかし、問題から逃げずに真ん中を歩く当事者が増えれば、社会は良くなるはずと信じている。信じられる理由は観光業界にはそんな先人がたくさんいるからだ。
私にとってその1人が小林天心だった。初対面はニュージーランド観光局長時代だったが、旅行企画の師匠だった。現場で奮闘している最中、しばしば希望に火をつける言葉を頂いた。「いくら安くできるかに頭を悩ます旅行企画は面白くなければ、やりがいもない」と厳しく、「売れ筋だけに固執する会社に未来はない」「自分が感動したことを顧客と共有するのが旅行企画の原点」と檄を飛ばす。触発された私はパンフレットの巻頭ページに売れ筋商品を置く慣例を破り、自分が本当に良いと思う商品を掲載するようにした。上司と衝突することもあったが、がぜん仕事が面白くなった。いまだから言えるいい思い出だ。
プレガイドツアー時代のカナダ・メープル街道の開発物語は特に痺れた。天心は一企業だけの恩恵にせず、政府観光局と航空会社を通して競合他社にも取り扱うよう働きかけ、業界を挙げて観光ルートの普及に取り組んだ。私はその話に刺激を受け、オフラインの目的地へのチャーター便を仕掛け、ライバルにも頭を下げて回った。最初は孤軍奮闘だったが人間万事塞翁が馬。実は天心が暗躍してくれたこともあり、結果的にたくさんの業界の同志が賛同してくれた。旅行業界は捨てたものではないなと思ったものだ。
天心の行動の根底にある論理は「旅行業は旅行文化の創造者」だった。旅行業を自分が生きていくための生業としてだけではなく、人々の心と人生を豊かにする文化産業として考えていた。
自分が本当に感動した体験を企画しているか。不振にあえぐ観光地に対し買い叩くのではなく共に考えているか。通過観光地から宿泊観光地へ変える、閑散期を埋める知恵と技術を磨いているか。そして時代を、文化をつくる矜持を持っているか。先人から受け継いだこの問いを、未来を担う次世代に贈りたい。
トラベルジャーナルの休刊に伴い、本コラムも最後となる。貴重なページを割いて自由に筆を執らせていただいた編集部と、トラベルジャーナルを通じて励ましを頂いた多くの読者には感謝しかない。
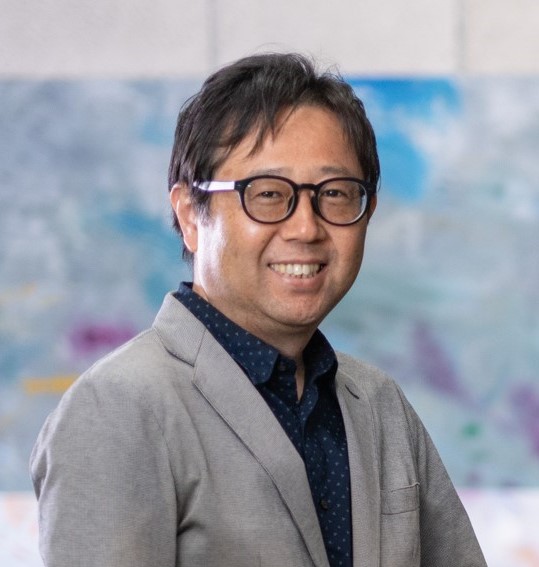
鮫島卓●駒沢女子大学観光文化学類教授。立教大学大学院博士前期課程修了(観光学)。HIS、ハウステンボスなど実務経験を経て、駒沢女子大学観光文化学類准教授、同大教授。帝京大学経済学部兼任講師。ANA旅と学びの協議会アドバイザー。専門は観光経済学。DMO・企業との産学連携の地域振興にも取り組む。
カテゴリ#コラム#新着記事
-
?>
-

旅行屋の矜持
?>
-

かけめぐる
?>
-

感謝の継承
?>
-

欧米で先行するアルコール離れ
?>
-

<寄稿>レジ袋有料化とインバウンド
?>
-

思いをはせよう
?>
-

地球に優しい報酬プログラム
?>
-

観光立国戦略の一考
 週刊トラベルジャーナル休刊のお知らせ
週刊トラベルジャーナル休刊のお知らせ