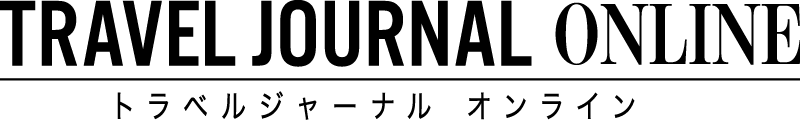
はるかなるオーセンティシティ
2022年9月5日 8:00 AM

分不相応。子供の頃、家族での外食で高額なメニューを勝手に注文しようとすると、そのようなニュアンスの言葉で叱られた。ただ、いまや死語。それどころか、その概念ごと消え失せた。事実、先日20代の相手との会話に用いて残念ながら意思疎通に失敗した。ポリコレたる正義の名の下における「多様性」を重視する現代とあれば、消滅するのは自然の流れだろう。しかしながら、このように当然のごとく使っていた言葉が退場していくことに年を経た自らを重ね合わせると複雑な思いだ。
分をわきまえているとスマートに感じさせる。力量以上のアウトプットは不格好。そのように刷り込まれた自分たちの世代たるものを思い起こす出来事が旅先であった。筆者は夫婦とも旅行業に携わる。ひとたび宿泊を伴う外出とあれば、会社としての販売実績が多いものの未体験のホテルやさまざまな媒体で話題の施設にステイすることが多い。さしずめ実費による実地研修だ。
今春以降利用したのは、すべていわゆる高級ホテルだ。3カ所とも実に豪華で瀟洒(しょうしゃ)なたたずまいだ。ただ、ホテルMにはなかった感覚がWやIには存在した。その違和感の正体は、人。Mのスタッフは誰もが気高く所作に余裕を醸す。若手も含め、ラグジュアリーホテルの勤務経験が豊富な人材で固めていることは明らかだった。ソフトとハードに一体感があった。
一方、WやIのスタッフはそのレベルでの経験が不足しているからか、あらゆる振る舞いが無理を感じさせて仕方ない。田舎のヤンキー上がりを彷彿とさせる担当者がしたり顔で話す「何かあれば私たち『キャスト』に」。……軽い、軽すぎる。その後、サイズの合わないパッツパツのスーツを着て、汗を拭きつつ客さばきに難儀する他のホテリエを見て気付いた。「なるほど、『ドタバタ喜劇のキャストたち』なのか」。なぜ自らオチを付けてモヤモヤ感を回収せねばならなかったのか、いまでも納得いかない。前の客が付けた手の汗で触る気になれない受付卓や、インク切れのため慌てて差し出された胸ポケットの100均の3色ボールペン。こうした鈍感さもハリボテ高級感の表現に随分と貢献していた。
真のハイクラスとカッコつけ感。その違いは、案外どんな客にも伝わる。人手不足を言い訳にせず、範となるコアスタッフを揃えずしてWやIの今後は暗い。何でも「コロナのせいで…」との言い訳が可能なサービスタイムは終了した。マネジメントの無能さに早く気付いてサービスを改善してほしい。そんな願いを顧客アンケートにしたためさせてもらった。
さて、サービスに対しての語りを読者諸氏はどう捉えるか。朝ドラの終了する時間には、ハッシュタグ「ちむどんどん反省会」がしばしばトレンド入りする。視聴者ではなく評論家、テレビを楽しむのではなく番組を評価する。投稿者のそのようなスタンスが支配的だ。これはネットが生み出した文化とでも言えようか。クチコミサイトが普及したゆえ、本来の目的よりも評価を残すことが一義的になった。他方、「医者でもないのに医療を語るな」とはここ数年よく見たコメントだが、医療サービスを提供される側の多くは医師免許を持たない市民だ。「電機メーカー社員でもないのに家電を語るな」と同じく極論に過ぎず、誰もが医療を語ってよいのは当たり前のことである。
経営学の博士号取得者から聞いた。売れない時は商品やサービス自体を見直す。買ってもらえない時は顧客に賢くなってもらうためのマーケティングが効果的な場合がある。私が論じるのは分不相応だが、後論は先述の問いに示唆を与えるように思う。

神田達哉●サービス連合情報総研業務執行理事・事務局長。同志社大学卒業後、旅行会社で法人営業や企画・販売促進業務に従事。企業内労組専従役員を経て現職。日本国際観光学会理事。北海道大学大学院博士後期課程。近著に『ケースで読み解くデジタル変革時代のツーリズム』(共著、ミネルヴァ書房)。