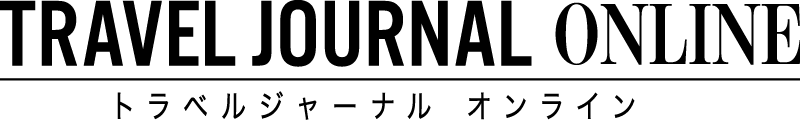
変えられないなら替えてみる
2021年2月8日 8:00 AM

オンライン販売全盛の時代に、旅行店舗は変われるか――。トラベルジャーナルの特集記事、4年前の発行号におけるテーマである。政府が緊急事態宣言を発出した昨春から、筆者は基本的に在宅勤務を継続している。経理等の事務作業で半月に1度程度は出所せざるを得ない状況下、このほど事務所内の資料整理を進めていると冒頭で記した記事に目が留まった。
「旅に関する本1500冊を備えカフェを併設した、旅のきっかけづくりを担うコンセプトショップがオープン」とある。ただ、この店はその後19年の年末に閉店した。「大人の女性向けに特化して旅情報の発信を担う、ショッピングモール内での追加出店」も20年9月で取り止めとなった。店舗の存在意義低下を打破するべく試みられた取り組みは、記事で紹介されてからいずれもわずか3年ほどで市場から姿を消した。「果たしてこの時代、旅行店舗は本当に必要なのか。そして必要とされる旅行店舗に変われるのか」。特集の結語は現在進行形の有効性を保持した問いかけであり、一層アイロニカルに感じられた。
それ以前の記事をさかのぼることはしなかった。だが、こうした記事に接するとこの5年いや10年ほど、同じ議論が繰り返されている気がしていてならない。旅行サービスの実務の世界では、もはや旅行サービスの進化を見つけることが不可能なのだろう。筆者が学術界との協働を進めたり研究の世界へ足を踏み入れたりしているのは、実務の世界で毎年あるいは数年ごとに繰り返される同じような言葉やコンセプトに辟易としてきたからなのだと、いま気付いた。
大企業のサラリーマンは自身に課された目標達成が第一であり、自社内で自らが関与しない事業や分野へ関心を持つことはほとんどない。旅行業の店舗のあり方について、社内異動によって初めて検討する立場となった人たちにとっては新鮮な議論のように見えることも多いだろう。しかし、長く当該議論の周辺に佇むものには、「またこの手の話か」と多くが思うのではないか。
もちろん、本質的な議論やあくまで実験的な取り組みとして進める事業もなかにはある。しかしながら、旅行業の店舗における変化を要求するのは常に外部環境の変化であるにもかかわらず、その変化に対して店舗そのものの変化は極めて遅い。昨今の閉店ラッシュはパンデミックによる需要蒸発との因果関係と捉える以前に、改革を実現できなかった末の無策によるお粗末な退場劇であることを忘れてはならない。
それでは、オンラインへの取り組みはどうか。やはり遅い。そして人材は不足し続けている。後者の課題についてデジタルメディアやトラベルテックのエグゼクティブへ話を聞くと、ほぼすべてがレガシー人材への失望を隠さない。アナログ一辺倒の人材でもデジタルシフトに向けた教育研修を施しさえすれば、デジタル人材へトランスフォーメーションできるとの期待はもう無理なのだという。デジタルを活用することで劇的なV字回復を果たしたことで有名となった老舗旅館へ取材した時にも、女将の言葉の端々から感じられた。デジタル改革は人を選ぶ。
どれだけ企業に貢献し続けてきても、レガシー人材とラベリングされた人は放出して、然るべき人材を投入しない限り存命できないとの危機感を持つ企業は少なくない。彼らにしてみれば、経営や事業執行の責を担う立場でレガシー人材が跋扈(ばっこ)しているところは、デジタル化への熱意は乏しく牧歌的なカイシャに映るだろう。いまやDXインフレの時期を迎え、デジタルを売りにしていた人は次の領域へとアップを始め出した。このギョーカイは2周遅れに突入した。
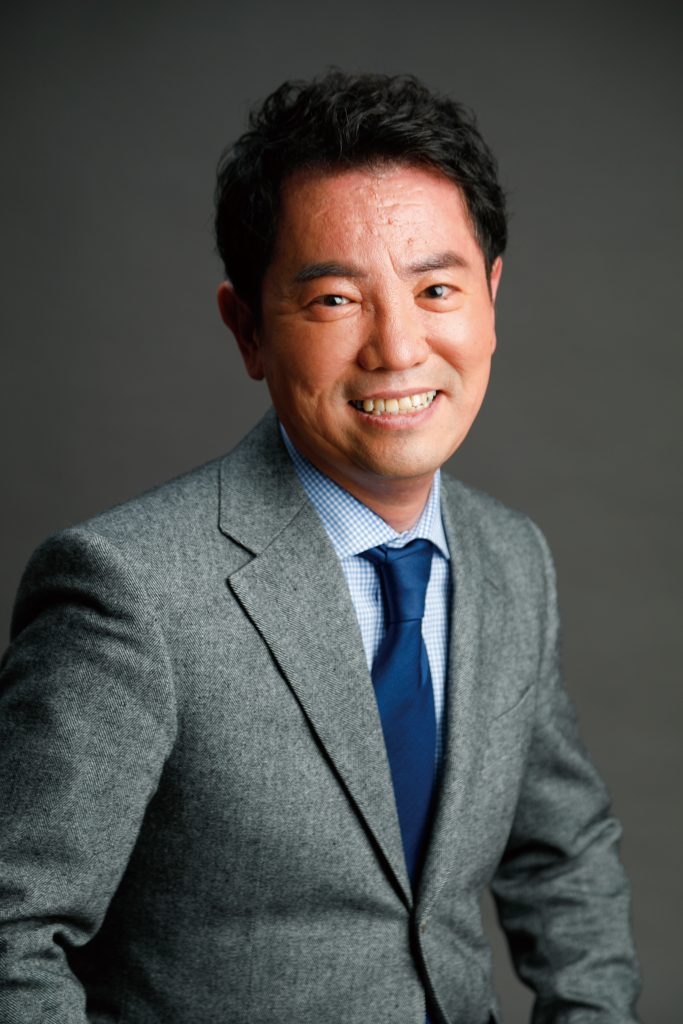
神田達哉●サービス連合情報総研業務執行理事・事務局長。同志社大学卒業後、旅行会社で法人営業や企画・販売促進業務に従事。企業内労組専従役員を経て、ツーリズム関連産業別労組の役員に選出。18年1月から現職。日本国際観光学会第28期理事。