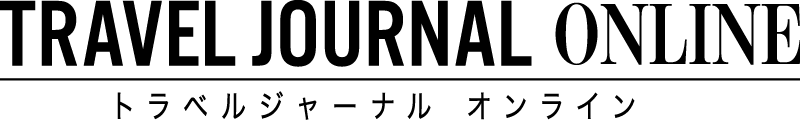
公害等調整委員会の荒井勉委員長が語る「裁判の世界と最近の動向」
2019年5月6日 8:00 AM

裁判や裁判所は決して社会に欠くことができない存在だ。ところが、多くの人々は裁判や裁判所とは日頃あまり縁がなく暮らしている。そんな裁判の世界について、長年にわたり裁判に携わった立場で説明してくれたのが荒井勉氏だ。
日本には最高裁が1カ所、高等裁判所が8カ所・支部6カ所、地方裁判所本庁と家庭裁判所本庁が各50カ所と支部203カ所あります。さらに簡易裁判所が438カ所。そして裁判官は約3000人、簡裁判事が約800人です。検察官が約2000人、弁護士は約4万人ですが、これら法曹の人口は欧米と比べてかなり少なく、人口10万人当たりの法曹の人数は米国の10分の1以下です。
司法試験に合格すると、司法修習生として2年間の研修を経て、弁護士、検察官、裁判官の3つから進路を選択します。それぞれ重要でやりがいのある仕事ですが、私は誰の利益にもとらわれず、自らの正義感に則って仕事ができる裁判官を選択しました。
裁判官は憲法上、完全な独立が保障されており、誰からも干渉されず、上司も存在しません。長年、民事や刑事の裁判を担当してきましたが、一度も権力などの圧力を受けたことも感じたこともありませんし、内部でそうした話を聞いたこともありません。あくまで裁判官の合議で判決を決めます。
裁判長は20年以上の経験者が務め、経験が5~20年の中堅が右陪席、経験5年未満の新人が左陪席を務めますが、合議に際しては同じ1票を持ち平等です。しかし、1対2で票が割れた場合はもう一度資料を読み直し、合議を尽くして全員一致の判断に至るように努めます。それくらい議論を尽くして合議体としての判断の質を高めておかないと、当事者から判決への納得を得られないからです。
裁判官にとって中立公正の意識が生命線で、強く意識しています。また、転勤は宿命です。勤務地は基本的に3年ごとに変わります。地元との癒着を防ぎ、全国どこでも国民が同じレベルの司法サービスを受けられるようにするためです。子供が受験期になると単身赴任になりますが、各地の土地柄の違いもわかり、楽しみに感じていました。
民事と刑事の現状
民事裁判は権利の実現を求める紛争であり、刑事裁判は犯した罪に対して処罰を与えるためのもので、同じ裁判でも性質が異なります。1つの交通事故でも、被害者が慰謝料や治療費等の損害賠償を求める民事裁判と、業務上過失致死傷として刑罰を与える刑事裁判の2つが行われることもあります。
民事裁判は、東京地裁民事部の場合、51カ部があり、裁判官約300人が裁判に当たっています。裁判は単独で裁くものが年間約200件あるほか、社会的な影響が重大な事件や判断の困難な事件は合議制で行いますが、この合議が70~100件あります。これだけ裁判を抱えているため、裁判官は必死で事件を処理しており、毎月5~6件の判決を書いているのが実情です。
事件処理の内訳は、判決が40%、和解が35%前後、その他が23%ですが、和解が極めて重要な解決手段です。むしろ判決より優れる場合が多く、双方が一定程度歩み寄ることで合意する手法は日本人の国民性にも合っていると思います。民事裁判では、負け筋の側にも2~3割の理があることが多いのです。それでも判決であればオール・オア・ナッシングになりますが、和解ならその2~3割の理を和解内容に反映させられます。和解のために当事者を説得する努力をして、どうしてもだめなら判決で、というのが私の考えです。和解が成立した際に双方から感謝される時が裁判官をしていてよかったと思える瞬間です。
刑事裁判は、検察官の起訴に基づき審理を行い、有罪・無罪の判定と量刑を判断するのが裁判官の役割です。日本の有罪率は99%に達しますが、自白事件が全体の7~8割と多いことに加え、否認事件でも検察官が圧倒的な証拠を保有することも関係しています。しかし、一番の要因は、起訴権限を独占する検察官がその裁量権を慎重かつ謙抑的に運用し、有罪にできそうなものしか起訴しない傾向があるからです。これには功罪両面がありますが、冤罪の防止にもつながっていると思われますし、起訴された者はそれだけで社会的に大きな不利益を被ることを考えると、運用は合理的ともいえます。
一般国民に司法参加を求め、裁判に市民感覚を反映しようと2009年に始まった裁判員裁判も丸10年となり、昨年12月までの9年間で1万2000件以上が行われ、約9万人の国民が裁判員または補充員として参加しました。米国の陪審員裁判との大きな違いは、米国は有罪・無罪を決められるのは陪審員だけで、量刑は裁判官が決めるのに対し、日本の裁判員は有罪・無罪と量刑の両方を判断し、裁判官と同等の権限が与えられている点です。裁判員裁判はここまで順調に進展してきましたが、それを支えてきたのは国民の誠実さと強い責任感です。裁判官として日本人の民度の高さを強く感じています。裁判員へのアンケート調査では、「やって良かった」「大変良かった」の回答が全体の95%以上で、多くの経験者が、皆で意見をぶつけ合い、一つ一つ丁寧に議論を積み重ねて結論に至る経験を大変貴重だったと述べています。
最近のカルロス・ゴーン氏の事件でも取り沙汰された人質司法の問題は、裁判所も問題意識を持っています。6月からは一定の事件で取り調べの録音録画も義務付けられるため、取り調べのありさまも変わってくるでしょうし、勾留や保釈に対する裁判所の見方にも変化の兆しが見られます。
天皇陛下のお言葉
高等裁判所の長官は天皇陛下の認証を受ける関係から、退官後に天皇陛下とお話をする機会に恵まれました。私は熊本地震の際に熊本の裁判所の職員が避難住民をピーク時に270人近く受け入れ、献身的にケアをし、多くの住民から感謝の手紙が寄せられた話をしました。そして、裁判所は法律に基づいて紛争を解決する機関であるけれども、真の解決のためには法律よりも前に人間的な優しい心がなければならないと考えており、このときの職員の姿はそれを示してくれ感動を覚えましたとお話ししました。陛下はじっとお聞きいただいたうえ、「裁判所の職員がそのように対応してくれたのは、裁判所は国民を守るところだという意識を持っていてくれたからではないでしょうか」というお言葉を返してくださりました。陛下が裁判所をそのように見てくださっていたことに感銘を受けた次第です。
裁判の根底には法律よりも前に人間的な優しい心があるべき裁判所がしっかり守っていけば、AI(人工知能)の時代になろうとも、裁判という仕事は人間が担い続けるだろうと思っています。
あらい・つとむ●1977年に判事補任官。京都、静岡、津、東京の各地裁勤務を経て、98年に東京地裁部総括(裁判長)。その後、司法研修所教官・事務局長、東京地裁民事部所長代行を務め、2011年宇都宮地裁所長、12年さいたま地裁所長、13年東京高裁部総括、14年東京地裁所長、15年福岡高等裁長官。17年の定年退官後に現職。