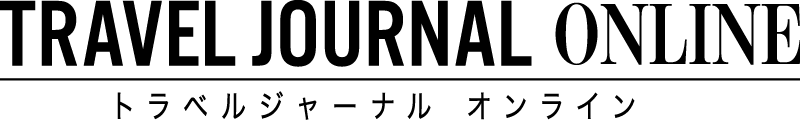
描こうグランドデザイン、 産業界主導で旅行業法改正を
2019年4月15日 8:00 AM

旅行業の基本原則を規定する旅行業法は、幾度かの改正を経て現在に至っている。その時々の社会状況を反映しつつ行われてきた改正は、結果的に旅行業の発展に貢献してきた。しかし旅行業を取り巻く環境がかつてないスピードで変化するいま、求められるのは産業界主導のよりアグレッシブな改正ではないだろうか。
戦後間もない1952年に不良・悪質業者の排除を主目的に制定された旅行あっ旋業法が、条文を全面的に書き直し、法律名も改めて71年に生まれたのが現行の旅行業法だ。当時の旅行業界は、60年代に始まった高度経済成長と64年の海外渡航自由化の追い風を受け、急成長を始めた段階だった。同時にパッケージツアーの登場やそれに伴うホールセーラーおよび代理店制度の発展など急激な変革を余儀なくされていた。そこで旅行業法では、不明確だった旅行業の定義を整理することで、運輸機関や宿泊施設の従属的な立場からの脱却を促し、旅行会社が社会的地位を法的に獲得することを後押しした。
その後、日本人の海外旅行の飛躍的な成長に伴い旅行業界も発展。一方で海外旅行者が急増し海外旅行中のトラブルも増加し、旅行中に発生した事故の責任の所在を巡る裁判が社会的な関心を集めることも増えてきた。そうした事態を踏まえ82年には消費者保護を前面に打ち出した大改正が行われ、主催旅行を明確に定義し、標準旅行業約款制度の導入などが図られた。
95年には13年ぶりに大改正され、主催旅行の責任が明確化され旅程保証が義務付けられた。主催旅行を手掛ける旅行業者にとっては厳しいハードルとなる旅程保証だが、その導入を積極的に進めたのは他ならぬ旅行業界自身で、自らの責任に一歩踏み込む白熱の議論を経たうえでの改正だった。旅行業者自身が自らを厳しく律することで、消費者の安心と信頼を獲得し旅行業者としての付加価値を高めようとした試みは、それまでの改正とは異なる視点に立ったものといえる。旅程保証導入の是非については意見が分かれるが、旅行を取り巻く環境や旅行の実態を追いかける受動的な改正ではなく、旅行業界自ら求めたアグレッシブな改正として注目されて然るべき改正だ。
この95年改正以降は再び現実への対応に追われた改正が続く。2004年改正では、バブル崩壊後に収益性の低下に苦しむ旅行業界の競争激化を背景に、主催旅行と手配旅行を曖昧にした販売が横行したこともあって、新たに企画旅行を定義することになった。
また03年の観光立国宣言により観光振興が国の施策に位置付けられたことで、地域の観光振興に目が向けられ、07年には地域の観光振興に資する着地型観光を普及する目的で、施行規則の改正により第3種旅行業務の範囲が拡大された。
その後、インターネットを利用した旅行取引の拡大や登山ツアーの安全確保、地域限定旅行業の創設、高速ツアーバスの安全性向上などの課題にガイドラインの策定や観光庁の通達で対処する一方、次の旅行業法改正に向け観光産業政策検討会が12年に設置され、ツアーオペレーター認証制度の導入などを盛り込んだ提言がまとめられた。この提言を受けて旅行産業のあり方や諸制度見直しの方向性を13年に設置された旅行産業研究会で検討。さらに16年からは新たな時代の旅行業法制に関する検討会で業法改正の方向性が固められていった。
その方向性が反映された改正旅行業法が18年1月に施行され、ランドオペレーターの都道府県への登録が義務化されると同時に、地域限定旅行業務取扱管理者資格が創設された。改正内容の検討段階では、海外OTAと競争条件が違い過ぎる点を是正するため、素材単品手配を旅行業法の対象外とする案や、海外OTAにも取引実態に応じた営業保証金を設定する案も議論されたが、改正に反映されることはなかった。それよりも急増するインバウンドへの対応の意味合いが強いランドオペレーターの登録制度導入が優先された格好だ。
業界に課されたもの
旅行業法制は消費者保護を旨とする規制的側面と、産業振興的側面を持つが、改正によってそのバランスをどう取っていくかは極めて難しい問題だ。ビジネス環境が急速にしかも激しく変化するなかで規制的側面を強く打ち出しすぎれば、新たな発想やビジネス創造のアイデアにふたをしてしまいかねず、日本だけがグローバルな流れに取り残され長期的にガラパゴス化を引き起こしかねない。反対に産業振興的側面が強過ぎる改正を行えば、消費者保護の観点がないがしろにされる懸念があるだけでなく、急速なルールチェンジは業界の混乱やモラル崩壊を招きかねない。
【続きは週刊トラベルジャーナル19年4月15日号で】[1]
- 【続きは週刊トラベルジャーナル19年4月15日号で】: https://www.tjnet.co.jp/2019/04/15/2019%e5%b9%b44%e6%9c%8815%e6%97%a5%e5%8f%b7%ef%bc%9e%e6%8f%8f%e3%81%93%e3%81%86%e3%82%b0%e3%83%a9%e3%83%b3%e3%83%89%e3%83%87%e3%82%b6%e3%82%a4%e3%83%b3%e3%80%80%e7%94%a3%e6%a5%ad%e7%95%8c%e4%b8%bb/