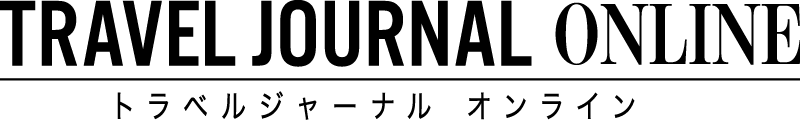
非日常の観光客を溶け込ませる努力をしているか
2018年11月19日 8:00 AM

ひと昔前の日本人の海外旅行を思い出してほしい。空港に2時間前に集合し、手荷物検査から出国手続き、搭乗プロセスまで事細かにレクチャーを受ける。添乗員なしツアーであれば、現地に着いてからの同様のプロセス、どこの出口に現地係員がいるかの案内を受け送り出される。空港のその場所は、たいてい少しセンターから外れたゾーンだ。中央のゾーンは飛行機に乗り慣れたビジネスマンがさっそうとチェックインを素早く済ませては検査場へと消えていく。
現地に到着すると係員の出迎えを受け、バスへと案内される。バスの中でのガイドの第一声はたいがい現地の言葉での挨拶、その後日本語でお国事情の説明が始まる。挨拶は、治安は、チップは。命の次に大切なパスポートはいつ何時でも肌身離さず。そんな話を聞きながら巡る観光地では決まって日本語での熱烈歓迎だ。立ち寄る店も観光客専用、夕食に案内されたレストランもみな似たような観光客ばかり。
ホテルに着けば外にでる猛者もおらず、旅の疲れもあってゆっくりお休み。朝はまた、なぜかミールクーポンを出す客は同じようなゾーンへと案内される。そんな時間を何度となく過ごして帰国の途へ。楽しかった旅の思い出を振り返る。現地係員、ガイドさん、店員さん、みんな親切だった。しかも何よりも、日本人観光客の私たちをきちんと区別して、快適に過ごせるように配慮してくれた。本当の意味でその地域に住む人々に出会うことはなかったけれど。
こうしてかつての旅人は、その地域に暮らす人々の日常や旅慣れたビジネスマンとは明確に区分けされた、旅行会社や現地会社が作り上げた非日常空間の中で過ごしていた。それは実際旅人にも心地よいだけでなく、地域の日常を脅かすこともなかった。何より非日常の空間を作り上げること自体がビジネスモデルだった。
近代の旅の大きな変化は、地域やさまざまなサービス業のシーンの「日常」に、「非日常」の旅人が共存を求めて分け入ったことだ。今では空港の旅行会社カウンターは影を潜め、航空会社でのセルフチェックイン。添乗員や現地係員の演説じみた案内に耳を傾ける必要もない。かつて旅人に何の興味も示さなかった、地元で人気のレストランやショップに多くの観光客が詰めかけ、それらの店が言葉やおもてなしを磨く。送客主体が旅行会社から個人に代わり、情報は加速度をつけ個人から個人へと拡散していく。
京都をはじめ、日本の観光地の路線バスや地下鉄に観光客が殺到し、通学や通勤の日常客が乗れない、といったことが課題になっている。しかしこれは必然。かつて観光客が路線バスに乗らなかったのは、団体旅行の時代には観光バスだったこともさることながら、そもそも観光客にとって路線バスが複雑怪奇なわかりにくい乗り物だったからだ。今では外国人観光客のスマホでも、グーグルなどで現在地と行きたい場所を検索すれば地図と乗るべきバスの系統、乗り場と時刻まで出てくる。世界中そうなってしまったのだから、もはや後戻りはできない。
今の時点で優劣をつけるとすれば、日常の空間に上手に非日常の観光客を溶け込こませる努力をしているか、未だに分離しようとしているかの違いだ。京都の交通情報は見事にオープン化されているし乗り場の案内もわかりやすい。一方で未だに路線バスの時刻などが検索エンジン向けにオープン化されていない地域もある。非日常を無理やり作り上げるより、どう日常のものを使い倒すかがこれからの観光地づくりには欠かせない。観光客にだけ愛想の良い、誰かだけが頑張る街はもはや時代遅れだ。

高橋敦司●ジェイアール東日本企画 常務取締役営業本部長 チーフ・デジタル・オフィサー。1989年、東日本旅客鉄道(JR東日本)入社。本社営業部旅行業課長、千葉支社営業部長等を歴任後、2009年びゅうトラベルサービス社長。13年JR東日本営業部次長、15年同担当部長を経て、17年6月から現職。